柔軟な働き方を実現する“フレックスタイム制”を知ろう

働き方改革 / ワークスタイル多様化
フレックスタイム制とは、労働者自身が出退勤時間と1日の労働時間を決められる制度です。昨今、柔軟な働き方の1つとしても取り上げられ、用語自体は多くの方が耳にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし、その特徴からか、会社が労働時間を把握しなくてよい、残業代を払わなくてもよい、といった誤った情報もたまに耳にします。
今回は、フレックスタイム制の特徴を改めて確認していきましょう。
目次
そもそもフレックスタイム制とは何か
フレックスタイム制とは、1日の労働時間を固定的に定めず、日々の出退勤時刻や労働時間を労働者が自由に決定できる制度です。導入時に一定期間(以降「清算期間」)における総労働時間を決めることを求められますが、それが清算期間の所定労働時間となります。出退勤時刻と1日の労働時間を自分で決められるだけですので、休憩時間、休日等のルールは通常の働き方と何ら変わりません。
フレックスタイムのメリットとデメリット
フレックスタイム制のメリットとデメリットには以下のようなものが考えられます。
<メリット>
・メリハリのある働き方に繋がる
定時のある働き方では、例えその日の業務がすべて終わっていたとしても、終業時間前に終業すれば早退扱いになってしまいます。一方でフレックスタイム制では、その日の仕事が終われば早く終業にできますので、業務状況に合わせたメリハリのある働き方ができます。
・優秀な人材の採用や定着率の向上に繋がる
現在、働きやすさやワークライフバランスを重視する労働者が増加しています。前述の通り、フレックスタイム制は始業終業の時間や労働時間を個人で自由に決められますので、個人に合った働き方を実現しやすくなります。働きやすい職場は、採用にも有利です。必ず優秀な方が採用できるとは言い切れませんが、応募が多ければそれだけ企業にとってもより良い方を採用しやすくなります。
また、育児や介護、通院等で今までであれば退職せざるを得なかった方も、働き続けるという選択をしやすくなります。
・業務効率の向上に繋がる
フレックスタイム制では、自分で労働時間を決められますので、今日は何時まで仕事をするか、何時間働くかを日々自分で考えます。そのため、業務の時間配分等を自然と考えるようになります。また、同じ部門やチームメンバーの勤務時間も把握しながら業務を遂行する能力も必要ですので、どうすれば効率よく進められるかを日々考え、調整する力にも繋がるでしょう。
さらに、出社が必要な業務であれば、通勤ラッシュを避けることもできますので、通勤ラッシュによるストレスも軽減でき、より多くの集中力や体力を業務に使えることも期待できます。
<デメリット>
・コミュニケーション不足が生じやすくなる
フレックスタイム制では、人によって、日によって、働く時間が異なりますので、コミュニケーション不足が生じやすくなる傾向にあります。社内コミュニケーションはもちろん、働く時間によっては顧客とのやりとりもしにくくなることもあります。
・時間外労働の把握、管理が難しい
通常の働き方では、1日8時間、週40時間を超えた部分が時間外労働になるため、今月どのくらい時間外労働をしているのかがわかりやすいです。例えば、10時間働いた日があれば、2時間は時間外労働していることが直感的にわかります。
一方でフレックスタイム制は、清算期間の労働時間を合計して、時間外労働の時間数を計算します(詳細は後述)。例えば今月の所定労働時間が160時間と決められているとき、極端な話、最初の16日間に毎日10時間働いたとしても、残りの期間に1分も働かなければ、その月の時間外労働は0時間になるわけです。これは非現実的な例ではありますが、要は、その月に何時間の時間外労働が発生するか清算期間が終わるまで確定しないため、気づいたら36協定の上限時間数を超えていた等が起こりやすいと言えます。
・生産性が低下する可能性がある
メリットで挙げた業務効率向上の裏返しとなりますが、働く時間帯が人によって異なるため、業務やスケジュールの調整が不十分だと、業務が止まってしまうおそれがあります。また、その日の労働時間を自分で決めることができるため、終業時間を決めず、だらだらと働く人が出ることも考えられます。
フレックスタイム制の導入手順
フレックスタイム制は会社が勝手に導入できるものではなく、以下の手順が必要です。
①就業規則等に、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める
②労使協定で以下の事項を定める(※印は任意)
<対象となる労働者の範囲>
全従業員を対象にしなければいけないわけではありません。「営業部」「人事部」のように部門ごとに対象を定めることもできますし、「Aさん」「Bさん」のように個人で定めることも問題ありません。ただし、同一労働同一賃金の観点から、正社員のみ、とすることには注意が必要です。雇用形態によらず、業務上フレックスタイム制を導入できるのかどうかで対象者を定めるようにしましょう。
<清算期間>
労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。例えば、「1か月で160時間は働いてもらいたい」と定めるときの「1か月」の部分です。上限は3か月です。
また、例えば清算期間が1か月の場合、毎月何日から何日までの1か月間なのか、清算期間の起算日も定めましょう。
<清算期間における総労働時間>
1つ前の項目「清算期間」に労働者が何時間働くべきか、を定めた時間で、これが清算期間の所定労働時間となります。先ほどと同じ例を使うと、「1か月で160時間は働いてもらいたい」と定めるときの「160時間」の部分です。当然、この総労働時間は際限なく定めることはできず、「1週間の法定労働時間に、清算期間の暦日数を7で割ったものをかけた時間数」以下で定める必要があります。文字ではわかりにくいため、以下の表を参照していただければと思います。
(出典:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
<標準となる1日の労働時間>
年次有給休暇を取得した際に⽀払われる賃⾦の算定基礎となる労働時間の⻑さです。1つ前の項目「清算期間における総労働時間」を、期間中の所定労働⽇数で割った時間を基準として定めます。
<コアタイム※>
労働者が1⽇のうちで必ず働かなければならない時間帯です。「10時から14時」のように具体的な時間を定めます。任意項目ですので、定めなくとも構いません。
また、曜日や日によってコアタイムを設けるかどうかが異なったり、時間帯が異なっても問題ありません。月曜日は定例会議があるためコアタイムを10時から15時にするが、それ以外の曜日はコアタイムなし、のようにすることも可能です。
<フレキシブルタイム※>
労働者が始業時間と終業時間を選択できる時間帯を定めることもできます。始業は5時から11時、終業は14時から22時の間で選ぶ、のようなルールを定めることができるということです。
労使協定に定めなければいけないのは上記項目までですが、以下の内容も定めておくことを推奨します。
・半休を取得したときの扱い、ルール
・清算期間の途中で入退社、休職等をした場合の清算期間と総労働時間(どこからが時間外労働扱いになるか)
・清算期間の総労働時間に実労働時間が足りなかったときの扱い(賃金控除か翌清算期間へ繰り越しか、繰り越しの場合の計算方法等)
③清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を所轄労働基準監督署長へ届け出る
④就業規則と労使協定を社内周知する
労働時間管理にはより一層の注意が必要
フレックスタイム制の法定時間外労働とは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた部分です。法定労働時間の総枠とは、1週間の法定労働時間に、清算期間の暦日数を7で割ったものをかけた時間数です。具体的な時間数は前掲の表を参照してください。
例えば、清算期間を1か月と定めた場合、その1か月で働いた時間を足していき、31日ある月であれば177.1時間を超えた分が法定時間外労働、つまり、割増賃金支払いの対象時間となるわけです。フレックスタイム制では、この法定労働時間の総枠を超えて働かせる場合に、36協定の締結と届出が必要です。
デメリットでも紹介した通り、1日の労働時間が非固定のため、自分の今の総労働時間がわかりにくいのがフレックスタイム制の特徴でもあります。清算期間の終了間際になって、このままだと36協定で定めた時間外労働の上限時間を超えてしまうとか、知らない間に超えてしまっていた、と慌てるケースも散見されます。
ここで注意したいのは、年次有給休暇の扱いです。フレックスタイム制では、年次有給休暇を使用した場合、制度導入時の労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」を働いたものとして、労働時間に加算されます。例えば、標準となる1日の労働時間を8時間と定めた場合、年次有給休暇を1日取得すると、その日は働いていない(労働時間0時間)のではなく、8時間働いた扱いになるわけです。固定時間制の働き方でたまに見る、時間外労働が多くなりすぎると労働時間の調整として年次有給休暇を取得する、ということがあまり意味を成さないことがおわかりいただけると思います。
そのため、上司や人事はもちろん、従業員自身も現在の総労働時間を確認できる仕組みを構築しましょう。また、フレックスタイム制の労働時間の考え方についても、従業員に定期的に周知したいものです。
働く時間帯に一定のルールを設けることも有効
また、労基法上の深夜(22時~翌5時)に働いた場合には、固定労働時間制の働き方と同様、深夜割増賃金の支払いが必要になります。極端な例ではありますが、「自分は夜型だから」とか「昼間に予定があるから」と、勤務時刻を18時から24時とした方がいる場合には、22時から24時までの2時間には、深夜業に対する割増賃金の支払いが必要です。
深夜も労働者の好きに働ける状態にしておくと、同じ時間働いても深夜の時間帯に働いた方が割増賃金がつくので支給額が増えます。深夜業を助長する上、昼間にしか働けない人が不公平に感じることは想像に難くありません。
そのため、コアタイムや、フレキシブルタイムを定めておくことは非常に有効です。例えば、出勤可能時間は5時から10時の間で決める、10時から15時までは必ず出勤、退勤は15時から22時までの間で決める、のようなものです。コアタイムを設けることで、チーム全員が必ず顔を合わせられる時間帯が作れるので、デメリットでも挙げたコミュニケーション不足の解消にも繋がります。
さらに、フレックスタイム制は深夜まで働いて翌早朝から働くことも可能なため、睡眠時間の減少も起こりやすく、労働者の健康管理にも十分注意しなければなりません。そのため、勤務間インターバル制度を導入し、勤務と勤務の間の時間を必ず一定時間空けるようなルールを整備することも非常に有効です。例えば、勤務間インターバルを11時間と設定すれば、退勤時間から11時間後ではないと出勤できません。休息時間を確保してもらうことで、無理な働き方を防止することが可能です。
フレックスタイム制は、生活と仕事の両立を考えると非常に便利な制度です。育児、介護、治療等との両立にも使え、コロナ禍での時差出勤に役立ったという声も聞きます。一方、労働時間管理が複雑になる面も強いので、制度の導入の際には、適切な労働時間管理の仕組みも併せて構築しましょう。

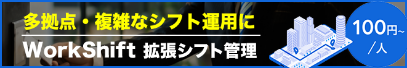


 今、注目が集まっている 『副業・兼業』という新たな働き方について
今、注目が集まっている 『副業・兼業』という新たな働き方について  【企業向け】サービス残業は違法?知っておきたいポイントまとめ
【企業向け】サービス残業は違法?知っておきたいポイントまとめ  年次有給休暇の管理で注意すべきポイント
年次有給休暇の管理で注意すべきポイント  増える!?多様な就労形態、勤務管理の方法は!?
増える!?多様な就労形態、勤務管理の方法は!? 