【偽装請負リスク回避】業務委託契約で「勤怠管理」はどこまで許されるか? 法的線引きと正しい時間把握の原則

勤怠管理
フリーランスや副業人材の活用が進む中、業務委託契約を結んで外部に業務を委ねる企業が増えています。しかし、業務委託契約では受託者の勤怠管理を行うことは、制度上そぐわないとされています。誤った運用は偽装請負と判断され、法的リスクを招く恐れがあります。本記事では、業務委託契約における勤怠管理の基本ルールから、偽装請負を回避するためのポイント、許容される時間把握の方法まで詳しく解説します。
目次
業務委託契約における勤怠管理の基本ルール
業務委託契約で外部人材を活用する際、多くの企業が悩むのが「どこまで管理してよいのか」という点です。結論から言えば、業務委託契約では受託者の勤怠管理を行うことは、制度上そぐわないとされています。まずはその理由を理解するために、雇用契約との違いを確認しましょう。
業務委託契約と雇用契約の違い
雇用契約と業務委託契約は、契約の性質が根本的に異なります。
雇用契約では、会社(雇用主)と従業員の間に「使用従属性」が生じます。使用従属性とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれる関係のことです。この関係があるため、会社は従業員に対して勤務時間や勤務場所を指定し、業務の進め方を指示できます。
一方、業務委託契約は事業者同士の対等な契約関係です。委託側と受託者の間には指揮命令権が発生しません。受託者は独立した事業者として、自らの裁量と責任で業務を遂行する立場にあります。
両者の違いを整理すると、雇用契約では労働基準法等による保護があり、残業代や有給休暇、社会保険の適用を受けられます。業務委託契約ではこうした保護がない代わりに、仕事の進め方や時間配分について高い自由度が認められています。
報酬の性質も異なります。雇用契約における賃金は、労働者が使用者の指揮命令下で労務を提供したことに対する対価です。一方、業務委託契約における報酬は、仕事の完成または業務の遂行に対する対価です。この違いを理解しておくことが、適切な契約運用の第一歩となります。
業務委託で勤怠管理ができない理由
業務委託契約で勤怠管理がそぐわない
理由は、受託者が労働基準法上の「労働者」に該当しないためです。
労働基準法第9条では、労働者を「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。業務委託契約の受託者は、委託元に使用される立場ではなく、独立した事業者として業務を遂行します。そのため、委託側が出退勤等の勤怠を指揮命令として管理することは想定されず、委託側は成果物の提出、進捗報告、作業日時の調整など、業務上必要な範囲での確認にとどめます。
業務委託契約では、受託者がいつ・どこで・どのように働くかは本人の裁量に委ねられています。委託側が出退勤時刻をチェックしたり、働く時間を直接管理したりする行為は、契約の趣旨に反するのです。
もし委託側が受託者に対して勤務時間の報告やタイムカードの打刻を求めた場合、それは実質的に「指揮命令による労働時間管理」を行ったとみなされる材料になり得ます。この状態は偽装請負と判断されるリスクを高めることになります。
業務委託契約の本質は「成果物や業務遂行に対して報酬を支払う契約」であり、時間そのものに対価を支払う賃金契約ではありません。この点を正しく理解しておく必要があります。
勤怠管理が招く偽装請負のリスクと罰則
業務委託契約の受託者に対して勤務時間の指定やタイムカードによる管理を行うと、実態により、いわゆる偽装請負に該当すると判断される可能性があります。実態によっては、いわゆる偽装請負と判断され、是正指導・行政処分の対象になる可能性があります。
偽装請負とは何か
偽装請負とは、実態としては雇用契約や労働者派遣契約に該当する働き方をしているにもかかわらず、契約上は業務委託(請負)と偽装している違法な状態を指します。
具体的には「実態が使用従属関係にあるのに、契約だけ業務委託にしている状態」のことです。企業が労働法上の責任やコスト負担を回避する目的で、このような形態が取られることがあります。
偽装請負の典型的なケースとしては、委託先にタイムカードで勤怠打刻をさせる行為や、シフトを一方的に決めて働かせる行為が挙げられます。受託者に対し、委託側がシフト指定やタイムカード承認など勤怠管理に当たる運用を行うと、実態として委託側の指揮命令下で就労していると評価され、いわゆる偽装請負(実態は労働者である)と判断されるリスクがあります。
日本の労働関連法では、労働者を他社の指揮下で働かせる場合は労働者派遣法に基づく許可等が必要です。これを偽装請負の形で行うことは、職業安定法や労働者派遣法に違反します。また、指揮命令や時間管理を伴う働かせ方は、労働基準法上も実質的に雇用契約とみなされるため違法状態となります。
偽装請負が発覚した場合の法的罰則
偽装請負が労働局等に認定された場合、企業には厳しい罰則や行政処分が科される可能性があります。
刑事罰としては、実態により無許可派遣や労働者供給等に該当した場合、1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金が科され得ます。厚生労働省東京労働局が公表している資料「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?」においても、業務請負に見せかけた違法な雇用を行った場合、委託企業(発注者)にこの罰則が適用されると明記されています。
出典:厚生労働省東京労働局「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/001.html
また、偽装請負を行った企業の責任者だけでなく、法人としての企業にも罰金刑(100万円以下の罰金)が科せられる両罰規定があります。
行政上の措置としては「改善指導・改善命令」が出されるケースもあります。改善命令を受けた場合は速やかに違法状態を是正する必要があり、従わない場合には事業の一部停止などより重い処分に発展することもあります。
企業が受ける社会的・経済的ダメージ
法的罰則に加え、企業が受けるダメージは多方面に及びます。
まず、悪質な偽装請負を続けている場合は企業名が公表されることがあります。実名公表されれば取引先からの信頼低下や人材採用面での悪影響は避けられず、事業継続そのものが危ぶまれるリスクすらあります。社会的信用の失墜によるレピュテーションリスクは、罰金以上に深刻な問題となり得ます。
民事上のリスクも見逃せません。偽装請負と認定され労働者性が認められた場合、受託者だった人から残業代の請求を受ける可能性があります。本来は業務委託料として一定額を支払っていたものが、実質的に労働時間に対する賃金と見なされ、未払い残業代を遡って請求されるケースです。
さらに社会保険(厚生年金・健康保険)の適用漏れについても、事後的に加入手続きを求められ、企業側が保険料を遡及負担しなければならなくなることも考えられます。このように、偽装請負は法的罰則だけでなく経済的負担や信用失墜など多方面のリスクを企業にもたらします。
偽装請負と判断されないための5つのポイント
偽装請負を避け、法律に抵触しないよう業務委託契約を適切に運用するには、委託側が踏み越えてはいけない線引きを明確に理解しておくことが重要です。以下に、企業が注意すべき5つのポイントを整理します。
1.指揮命令を出さない
業務委託では受託者に対して業務の指示・命令を行ってはいけません。
「いつ・どこで・どのように働くか」を細かく指示する行為は、使用者としての指揮命令と判断されます。開始時間や終了時間、作業手順などを企業が指定すれば、それは雇用関係と同様の支配下に置いているとみなされる可能性があります。
受託者はあくまで自らの裁量で業務を遂行する立場です。企業側は成果物の受領や業務範囲の確認に留め、作業の進め方には干渉しない姿勢が求められます。業務の依頼はあくまで「何を・いつまでに」というアウトプットベースで行い、プロセスへの介入は控えましょう。
2.労働時間の管理をしない
出退勤時刻や作業時間の管理(勤怠管理)を企業が行わないようにします。
タイムカードでの打刻、勤怠管理システムへの入力要求、日々の勤務報告を義務付ける行為は避けなければなりません。業務委託契約では「何時間働いたか」は本来問題にならず、契約上の責任(成果や納品)が果たされていれば時間の多寡は問わないのが原則です。
企業側が労働時間を逐一把握しようとすると、それ自体が指揮監督下で働かせている証拠となりかねません。時間ではなく成果で評価する姿勢を徹底することが大切です。
3.報酬の計算方法に注意する
報酬形態が実質的に「時間給」「月給」のようになっていないか注意が必要です。
「1日〇円の固定支払い」「月額固定報酬+α」といった形で、働いた日数や月数に応じて支払う契約は、給与のように見做される恐れがあります。
本来、業務委託の報酬は請負契約であれば成果物に対して、準委任契約であれば一定期間の業務遂行に対して支払われるものです。準委任契約で時間単価×稼働時間で報酬を算出するケースもありますが、あくまで「契約上定めた業務遂行の対価」であることを契約内容で明確化しておく必要があります。
4.受託者を自社に専属させない
特定の受託者を自社業務だけに拘束しないよう注意が必要です。
実際に1社に割く拘束時間が長すぎて他の仕事を受けられない状況であったり、毎月固定の報酬を支払って事実上フルタイムで働かせていたりすると、「専属性が高い」と判断され雇用に近いとみなされる場合があります。
業務委託では本来、受託者は他のクライアントの仕事をする自由が保証されるべきです。契約上、副業禁止や競業避止などの特約で過度に受託者の活動を制限しないようにしましょう。「週5日フルタイムで常駐し固定月額報酬を支払う」といった形は極力避け、必要に応じて正式な雇用・派遣契約を検討すべきです。
5.業務上の用具・経費負担の扱い
仕事に使う機材や備品、経費は原則として受託者側が負担する形にします。
雇用契約では会社がPCや制服を貸与し、業務経費も支給することが多いですが、業務委託では受託者が独立事業者として自前の道具を使い、自ら経費処理するのが本来の姿です。
実務上、セキュリティの理由から委託先企業がPCを貸与するケースや、取材費等を実費精算することもあります。しかし全て会社支給・貸与が当たり前の状態だと、雇用に近い扱いと映ります。必要な経費精算は契約書にルールを定め透明性を確保しつつ、受託者が自己負担する範囲も明確にしておくとよいでしょう。
業務委託で許容される時間把握の方法
業務委託で受託者の勤怠管理は原則NGですが、業務上どうしても時間の把握や調整が必要となる場面もあります。最小限の範囲で業務進捗を管理する方法を取ることが現実的な対応です。
契約時に業務量や納期を明確にする
契約段階で業務内容・期間・納期を具体的に定めておくことが重要です。
業務委託契約書において「○月○日までに△△を提出」等、期待する成果(成果物・成果基準)を合意します。
また準委任契約では、業務量の目安として「月○時間程度(または上限○時間)」といった工数見込みを合意することがあります。この場合でも、報酬は契約で定めた業務遂行の対価であり、委託側が受託者のシフト・勤怠を管理する趣旨ではないことを、業務範囲・裁量・報告方法とあわせて明確化します。
ただし「平日毎日10時~16時に必ず作業する」といった具体的な稼働時間の指定はできません。週や月単位で必要な作業時間の目安を示すことは許容されますが、日々の稼働スケジュールは受託者の裁量に委ねる必要があります。
業務の性質上、作業時間帯や作業場所に一定の制約が生じる場合があります。この場合は、制約が必要となる理由(例:現場対応・設備利用・セキュリティ等)と条件を契約書に明記し、委託側の関与は納期・品質・安全等の観点から必要な範囲の調整にとどめます。
なお、委託側が受託者の出退勤・勤務時間を承認するなど勤怠管理として運用すると、直接の指揮命令関係と評価され、いわゆる偽装請負と判断されるリスクがありますので注意が必要です。
成果物・進捗ベースで業務を管理する
勤怠管理ができない代わりに、進捗管理・成果管理に重点を置く方法があります。
具体的には、受託業務についてマイルストーンや区切りとなる成果物を設定し、段階的に進捗を確認するやり方です。「週次で簡単な進捗レポートを提出してもらう」「ウェブ制作であれば、サイトマップ→デザイン案→コーディングと段階を追って成果物をレビューする」等の方法があります。
この方法であれば、労働時間ではなく成果物の出来具合で仕事の状況を把握できるため、指揮命令による勤怠管理とならずに済みます。
進捗報告の頻度や方法については、最初に契約書や発注書で「毎週金曜にメールで報告」「月末に月次報告書提出」などと決めておくとスムーズです。「何時間働いたか」ではなく「仕事がどこまで進んだか」に着目することがポイントです。
受託者自身による時間記録・報告を活用する
準委任契約で時間単価により報酬を算定する場合、精算のために稼働時間の報告を求めることがあります。このとき、委託側の関与は報酬精算・進捗管理に必要な範囲にとどめ、受託者が自己の裁量で記録した工数(タイムシート等)を提出する形とします。
なお、委託側が受託者に対して出退勤・勤務時間の管理を行うなど、直接の指揮命令関係がうかがわれる運用となる場合は、いわゆる偽装請負(実態は労働者派遣)と評価されるリスクがあります。
時間計測ツールを導入する場合も、それを労務管理ではなくプロジェクト管理の一環として扱うことが重要です。受託者の合意なしに監視のような使い方をすれば労働者性があると判断される可能性もあるため、あくまでも自発的な報告ベースで時間情報を共有してもらうことが大切です。
契約書で禁止事項・注意事項を明示する
業務委託契約書を必ず締結し、権利義務関係を明確化することも正しい運用の原則です。
契約書には、業務内容・報酬額・支払条件・納期のほか、禁止事項として「受託者が従業員と混同されるような指揮命令下で業務を行わない」旨や「発注者は受託者の労働時間を管理しない」旨を記載する例もあります。
例えば、契約書の条項に「受託者は自己の裁量と責任において業務を遂行するものとし、発注者は業務の進め方や時間配分に干渉しない」といった文言を入れることで、双方がその認識を共有できます。書面で約束することで「つい管理し過ぎてしまった」という事態を防ぎ、偽装請負への発展を抑止する効果があります。
なお、契約書で「本契約は雇用関係ではない」と謳ってあっても、実態が伴っていなければ法的には通用しません。しかし両者の認識を揃える意味で契約書を交わす意義は極めて大きいと言えます。
業務委託契約を適正に運用するために押さえておきたいこと
業務委託契約は雇用契約とは根本的に異なる契約形態であり、勤怠管理は原則として適しません。受託者の働き方に企業が過度に干渉すると、偽装請負と見なされ法律違反となるリスクが高まります。
本記事のポイントを整理すると以下のとおりです。
- 業務委託契約では指揮命令権がなく、受託者の勤怠管理は原則しないこと
- 偽装請負は、実態により労働者派遣法・職業安定法違反となり得て、類型によっては 1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金の対象となり得る
- 指揮命令・労働時間管理・専属拘束・時給制報酬は偽装請負のリスク要因
- 契約時に業務量・納期を明確にし、成果や進捗ベースで管理する
- 時間把握が必要な場合は受託者自身による自己申告形式を活用する
- 契約書に禁止事項を明記し、双方で認識を共有する
業務委託契約を適正に運用するためには、「何を・いつまでに」というアウトプット面で管理し、プロセスへの干渉は控えるという姿勢が大原則です。法律の線引きを守りつつ、委託側・受託側の双方にとってメリットのある契約関係を構築していきましょう。

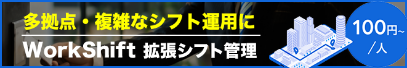


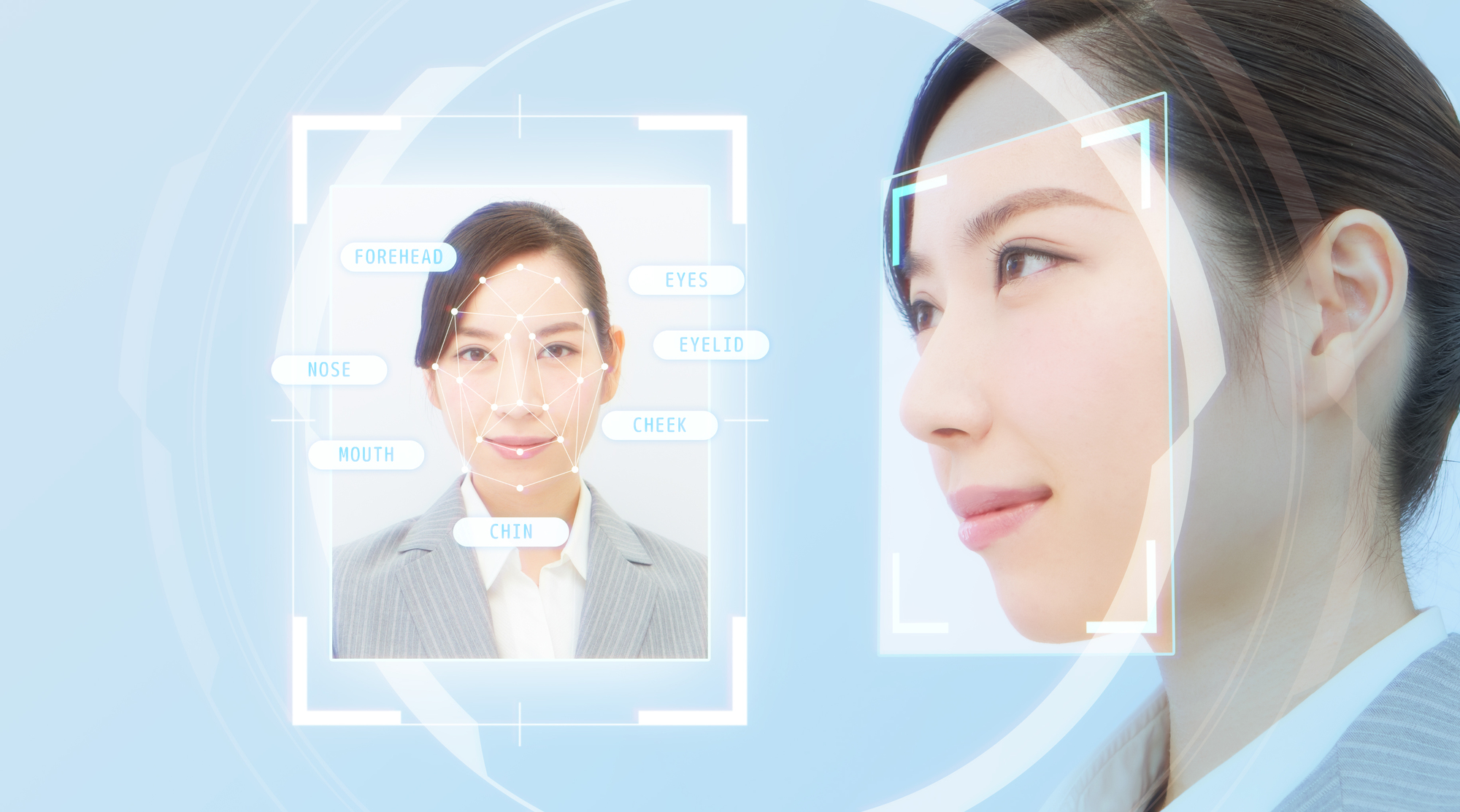 顔認証 勤怠管理は本当にコスパが良いのか? コストと精度の比較検証、デメリットを解消するシステム選び
顔認証 勤怠管理は本当にコスパが良いのか? コストと精度の比較検証、デメリットを解消するシステム選び  労働時間の素朴な疑問を解消!
労働時間の素朴な疑問を解消!  【勤怠管理で重要】6時間勤務の休憩時間は?休憩のルールや注意点
【勤怠管理で重要】6時間勤務の休憩時間は?休憩のルールや注意点  勤怠管理における中抜け時間の取り扱いや注意点、知っておきたいポイントまとめ
勤怠管理における中抜け時間の取り扱いや注意点、知っておきたいポイントまとめ  ICカードで勤怠管理する方法|メリットやデメリット、他の勤怠システムの違い
ICカードで勤怠管理する方法|メリットやデメリット、他の勤怠システムの違い