多様な働き方に対応した『労働時間の管理』のポイントとは

目次
『労働時間の管理』は企業の責務
労働基準法及び労働安全衛生法上、企業は社員の労働時間について適正に把握する責務を有している。
そのため、労務管理部門では社員一人ひとりの始業時刻や終業時刻、休憩時間などを適切に管理し、労働時間を正しく把握しなければならない。把握した労働時間に関する情報は、「働いた時間に応じた適正な給与支払い」「長時間労働の抑制による健康障害の削減」などに活用することが必要とされている。
ただし、現在、企業で勤務をする労働者は、必ずしも全員が同じような立場で働いているわけではない。例えば、次のような多様な勤務形態が併存している。
1.テレワーク
2.短時間の勤務
3.フレックスタイム制
4.派遣労働
5.副業・兼業
6.業務委託契約
そのため企業側には、これらのさまざまな働き方に対応した『労働時間の管理』を実践することが必要とされている。
「テレワーク」でも勤怠管理は必要
それでは、勤務形態別の『労働時間の管理』について、主なポイントを具体的に見ていこう。初めにテレワークを行う社員の場合である。新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、在宅勤務などのテレワークを採用している企業も多いだろう。
企業に勤務する労働者には労働基準法、労働安全衛生法などの労働基準関係諸法令が適用されるが、この点は在宅勤務などのテレワークをしている社員も例外ではない。そのため、テレワークを行う社員についても始業時刻や終業時刻、休憩時間などを適切に管理し、個々の労働時間を正しく把握しなければならない。
しかしながら、職場に出勤をしていないのだから、タイムカードやICカードなどで管理をすることができない。そのため、出退勤の時刻などを客観的な方法で管理するには、工夫が必要になる。例えば「始業時、終業時に上席者に対するメール連絡を義務付ける」「パソコンの使用時間、勤怠管理システム、ウェブ会議システム、チャットアプリなどを活用する」などに取り組む必要があるだろう。
また、テレワークを命じると、通常よりも労働時間が長くなる社員が存在することがある。そのため、長時間労働が発生しないよう「時間外・休日・深夜労働を禁止または許可制にする」「時間外、深夜、休日のメール送付を禁止する」「深夜、休日は社内システムへの外部アクセスを制限する」などのルールも整備が必要である。
加えて、テレワーク中には中抜け時間が発生しがちである。中抜け時間とは私用のため一時的に仕事から離れる時間で、例えば「保育園に子供を迎えに行く」「銀行や役所に手続きに行く」「高齢の家族の面倒を見る」などの時間が発生しやすい。そのため、このような時間について「休憩時間として扱う」「時間単位の年次有給休暇として扱う」など、取り扱いルールを事前に決定しておくことも不可欠といえよう。
休憩時間に注意したい「短時間の勤務」
次に、短時間の勤務をする社員の『労働時間の管理』を考えてみよう。短時間正社員やパートタイマー、アルバイトなど、働く時間数が他の社員よりも短いケースでは、一般的な『労働時間の管理』に加えて注意をしたい点がある。休憩時間の管理である。
1日の労働時間が6時間以下の場合、法律上は社員に休憩時間を与える必要はない。ただし、6時間を超えて8時間以下の場合には、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与える必要性が生じる。
そのため、例えば1日の労働時間が12時から18時までの6時間のパート社員の場合、法律上は休憩時間を与えなくてよいことになる。しかしながら、仮にこの社員に10分間の残業が発生すると1日の労働時間が6時間を超えるので、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
しかしながら、このようなケースでは、パート社員に対して労働時間の途中に休憩を与えることは簡単ではない。退勤時刻の18時から45分の休憩を与え、その後に10分間の残業を行わせることもできなくはないが、実務上は18時から休憩をせずに10分間の残業を行うケースが多いだろう。その結果、法令違反となりがちである。
休憩時間の管理に関するこのような事態を回避するには、「短時間勤務の社員には残業を命じない」「短時間勤務の社員に残業が発生した場合には、別の社員に業務を引き継ぐ」「短時間勤務の社員には、残業の有無にかかわらず45分間の休憩を与える」などのルールをあらかじめ整備しておくことが必要といえよう。
「フレックスタイム制」の残業管理は清算期間単位で
次は、フレックスタイム制で勤務する社員のケースである。フレックスタイム制とは、日々の始業・終業時刻を一定の範囲内で社員自身が決められる制度である。勤務時間を個人の事情に合わせて調整できるため、ワークライフバランスの実現に適した制度ともいわれている。
しかしながら、業務の開始時刻などを社員自身が決定するからといって、企業側の「労働時間を管理する責務」が免除されるわけではない。従って、フレックスタイム制で勤務する社員についても始業時刻や終業時刻、休憩時間などを適切に管理しなければならないのだが、通常勤務の社員の『労働時間の管理』とは異なる点が多いため注意が必要である。
特に気を付けたいのが、残業時間の管理である。フレックスタイム制で勤務をする社員については1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えたりした場合に、直ちに時間外労働となるわけではない。3カ月以内の清算期間について働くべき総労働時間をあらかじめ定め、その時間数を実際の労働時間が超えた場合に初めて時間外労働となるのが原則である。
例えば、清算期間を1カ月とし、その間に勤務すべき総労働時間を170時間に定めたとする。この場合、仮に1日10時間の労働を行った日があったとしても、清算期間である1カ月の総労働時間が170時間以内なのであれば時間外労働は発生したことにならず、割増賃金の支払い義務も生じない。
一方、当該期間中の総労働時間が180時間になるようなことがあれば、10時間の時間外労働が発生したことになるので10時間分の割増賃金の支払いが必要になる。通常勤務の社員とは残業時間の概念が大きく異なるため、誤りのないように管理をする必要があるだろう。
派遣元の36協定の確認が必要な「派遣労働」の残業管理
派遣社員は自社が直接雇用しているわけではなく、人材派遣会社などの他社と雇用契約を結んでいる労働者である。ただし、派遣社員の労働時間を管理する責務は、実際の就業場所である派遣先企業に課されている。
従って、派遣社員についても、自社の社員と同様に始業時刻や終業時刻、休憩時間などを適切に管理し、個々の労働時間を正しく把握しなければならない。さらに、把握した労働時間に関する情報は、労働者派遣契約を結んだ人材派遣会社に月に1回以上、通知をすることも求められる。
また、派遣社員に残業を命じる場合には、注意が必要である。法定労働時間を超えて時間外労働をさせるには36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)が必要だが、派遣社員に適用される36協定は自社の協定ではなく、派遣元である人材派遣会社の協定だからである。
そのため、派遣社員の残業管理上は、事前に人材派遣会社の協定の内容を確認することが必要になる。自社の36協定と派遣元企業の協定とでは、「延長することができる時間数」の定めなどが異なることも少なくない。従って、人材派遣会社の協定を確認の上、当該協定に定められた範囲内で残業を命じるようにしたい。
なお、派遣社員の労働時間の記録に関する書類は、派遣先企業にも一定の保存義務が課されている。派遣社員の退職後、早々にタイムカードを処分してしまうなどのことがないようにしなければならない。
「副業・兼業」で必要な労働時間の通算
副業や兼業を行う社員の『労働時間の管理』は、自社と他社の労働時間の通算処理を正しく行うことがポイントになる。社員が自社以外の企業でも勤務している場合、残業時間の管理は2社の労働時間を合算して行わなければならないからである。その結果、自社の所定労働時間内の勤務が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になるケースもあることに注意したい。
例えば、他社で1日5時間勤務を行っている人材を、自社で1日4時間勤務のパート社員として雇用したとする。この場合、自社と他社の所定労働時間を通算すると9時間となり、1日の法定労働時間である8時間を1時間超過してしまう。
このようなケースでは、後から契約した自社での労働時間のうち1時間は、時間外労働として取り扱わなければならない。そのため、自社では所定労働時間内の勤務であってもそのうち1時間は残業扱いとなり、割増賃金の支払いが必要になるものである。
このような取り扱いを適切に実施するには、副業や兼業を行う社員について副業・兼業の内容を届け出るルールを明確化することが重要である。
ただし、労働時間を通算するのは、副業や兼業が労働基準法の対象となる就業形態で行われている場合などに限定されている。従って、副業などが企業に雇用されて働いているケースであれば通算の対象となるが、「個人事業主として働いている」「会社を経営している」などの場合には対象にならないのが通常なので、間違えないようにしたい。
労働時間の管理対象にならない「業務委託契約」
最後は、請負契約や委任契約などの業務委託契約に基づく勤務である。これは労働者が個人事業主の立場で企業から業務を受注し、勤務するケースである。労働者には自身の知識やスキルを活用して組織に縛られずに働けるというメリットがあり、企業側にも社会保険料負担などが発生しないなどのメリットが存在するため、採用されることのある契約形態である。
企業によっては、このような労働者に対して「請負社員」「委託社員」など、“社員”という文言を付した呼称を使用していることがある。あたかも自社で雇用している労働者であるかのような呼び名だが、個人事業主の立場で働く人材は自社と雇用契約を締結しているわけではないので自社の社員ではない。
そのため、自社の社員や派遣社員とは異なり、労働基準法などの適用対象にならない。従って、企業側が請負契約や委託契約などに基づく労働者の『労働時間の管理』を行うことはできないので、注意をしたい。
仮に、このような形態で働く労働者の出退勤や勤務時間の管理などを行った場合には、「業務委託契約は形式的なものであり、実態は自社の社員と変わらない」との判断が労働局などによって行われることもある。その結果、偽装請負を問われるケースもあるので、十分な注意が必要である。
以上のように、現在の労働環境は勤務形態の多様化に伴い、『労働時間の管理』が非常に複雑化している。割増賃金の計算も煩雑になり、給与の支払いミスも起こりやすい。
そのため、勤怠管理業務を手作業やエクセルなどに依存するのは、必ずしも適切な管理施策ではない。誤りのない円滑な『労働時間の管理』を実現するには、勤怠管理システムの活用などを検討するのもひとつの方法といえるだろう。

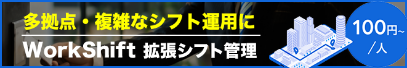


 増加するメンタル不調者への対応を考える
増加するメンタル不調者への対応を考える  タイムカードを見直して生産性向上!働き方改革で時間効率を最大化する取り組み
タイムカードを見直して生産性向上!働き方改革で時間効率を最大化する取り組み  工数管理ツールの選び方とは?種類や機能、Excelとの違いを解説
工数管理ツールの選び方とは?種類や機能、Excelとの違いを解説  厚労省、監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表
厚労省、監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表  勤怠管理における中抜け時間の取り扱いや注意点、知っておきたいポイントまとめ
勤怠管理における中抜け時間の取り扱いや注意点、知っておきたいポイントまとめ 