コロナ後のオフィス出社が前提となった労働環境下におけるメンタルヘルス問題

全世界を震撼させた新型コロナウイルスは、一定の終息はあったことから、多くの企業でテレワークに比重が置かれていた労働環境からオフィス出社が前提となる労働環境に移行されています。見方を変えると単に「元に戻る」状態ではあるものの環境の変化は労使間において一定のストレスになることもあります。今回はその中でもメンタルヘルス問題にフォーカスをあて解説します。
業務の遂行方法
コロナ禍においては一部のエッセンシャルワーカーを除き、各種ITツールを活用したテレワークが普及し、一定の成果を挙げた企業も多いでしょう。多くの企業で「テレワークはできない」とトライすることなく判断されていたものが、半ば強制的にテレワークが開始されました。テレワーク中はチャットツール等を用いて、「視覚的に」業務の連絡、報告が行われることから、業務遂行にあたっての備忘録としての機能を備えているという性質がありました。もちろんこれは形に残らない「会話」での業務の連絡、報告は指揮命令系統が正確に伝わっていない場合、認識齟齬が生じるリスクや、備忘録としての機能が備わっていないがゆえに業務の成熟度が低くなる(例えば差し戻しが生じる)点がリスクとして挙げられることから合理的な手法であることは否定できません。
他方、対面出社後も同じ部署内(あるいは「隣の席」であっても)であるにも関わらず(テレワーク時と同様に)全てチャットツールで視覚的に業務の連絡、報告体制が敷かれているケースがありますが、この点に違和感を覚えるビジネスパーソンからの相談が増えています。視覚的な業務の連絡、報告は、平たく言うと、感情が伝わりにくく「冷たい」という印象を抱かれやすいため、メンタルヘルスの観点からも(何のために毎日時間をかけて出社しているのか等の葛藤)プラスに作用するケースは多くありません。
確かに視覚的な指揮命令系統は少なくとも「聞き間違い」のリスクを回避できるだけなく、「振り返り」もできる(指揮命令者は当該明示内容に誤りはなかったか、指揮命令の受領者は当該内容の誤認識はなかったか)ため、多くのメリットがあります。ただし、物事には限度というものがあり、画一的に「視覚的な指揮命令のみ」で進行するというのは、事実上テレワークを廃止または大幅縮小し、わざわざ法律上支給義務のない通勤手当を支給してまで出社を命じている意味も乏しくなると考えます。
上司との距離感
上司との距離感について、テレワーク下においては、物理的に相談先の上司の状況が見えず、ある意味では自分のタイミングで相談(または報告・連絡)できていたものと考えられます。しかし、出社後については、上司の動向がほぼリアルタイムで確認できるため、相談のタイミングについては一定のモラルが求められます。そうなると早期に相談すべき案件も含めて「抱え込み」が起きてしまうと言ったケースが増えています。そうなると上司から「なぜもっと早く相談しなかったのか?」とのやりとりが発生し、堂々巡りになることでストレスを抱え込む労働者が散見されます。もちろん、テレワークであっても結果的にタイミングが悪い相談はあったのかもしれませんが、お互いの状況が見えないという大義名分があったため、問題視されることはなかったと考えられます。
本来、テレワークが例外でありオフィスへの出社は「元の状態に戻っただけ」と考えられますが、一度体感したことは人間誰しも完全に忘れ去ることは難しいと言えるでしょう。メンタルヘルス上の問題として「テレワークの方が良かった」と考える労働者が一定数存在します。しかし、労務提供場所は本来、会社の指揮命令によりますので、労働者の一存で決められる問題ではありません。また、そのような悩みは上司に相談することは難しく、悩みをそのまま抱え込んでいるというケースも多く存在します。
時間外労働との向き合い方
働契約上、客観的な労働時間の記録は必要不可欠であることからテレワーク時であってもそれは例外ではありません。しかし、テレワーク時においては多くの場合、自宅が「職場」となることから、「仕事と生活の切り分けが難しい」との声が多く上がりました。これは自宅と職場が同じ空間であるため、構造上、両方が密接した時間帯にできてしまうためと考えられます。しかし、その感覚で対面業務に戻ってしまうと、これまで容易にできていた私生活上の内職作業等へ割り振れる時間が少なくなるため、ワークライフバランスの両立ができないとの感覚に苛まれる労働者が散見されます。しかし、本来「働く場所」は会社の指揮命令の範囲内であるため、「働く場所」が「本来の場所に戻った」にも関わらず(実際には時間外労働時間数がそこまで増えているわけではないにも関わらず)相談事例として、「仕事一辺倒になっている」との悩みが挙がってくることがありますが、それは、そもそもの趣旨に立ち返ると適切とは言い難く、他の解決方法(限られた時間内で時間外労働となることなくどう効率よく仕事をこなすか)を模索する必要があります。
また、もう1つの問題として、1点目の論点と類似の論点ではありますが、自宅が「職場」である場合は、通勤時間がないため、対面業務に戻った際にはテレワーク時と比べて「時間がない」との感覚に苛まれ、その焦りが引き金となり、納期遅れやミスが生まれ、それゆえにメンタルヘルス上も良好な状態でなくなることが確認されています。
そもそもテレワーク時に本来の対面業務であれば、通勤時間に相当する時間帯から仕事を開始していたのであれば実質的にはその時間は労働時間ではないかとの議論(ただし指揮命令があったとは言い難い)もあります。
メンタルヘルス上の最も大きな問題として、外見から容易に判別できる怪我や負傷と異なり、心身の内面に潜んでいる問題であるため、視覚的にはキャッチすることが容易ではないことです。時間外労働とメンタルヘルス上の問題は(過去に世間を震撼させた過労死自殺問題等もあり)非常に根深く、会社としても労働者からの積極的な申し出が無くても、上長が違和感を覚えた際には一定の措置を講ずべきことは「安全配慮義務」としても必要不可欠です。
私傷病休職
メンタルヘルス問題が契機となり、勤怠不良の状態に陥ったとしても直ちに解雇できるわけではありません。このような場合は私傷病休職制度の活用が望まれます。まず、「休職」とは解雇に至るまでの猶予措置としての機能を持ち、労働契約上の地位は存在しつつも労務提供が免除される制度です。労働基準法上、「休職」という法律条文は存在しませんが、時代背景条上も増えつつあるメンタルヘルス問題に対応する制度として、私傷病休職は必要な制度です。また、労使双方に重要な論点となる、私傷病休職期間中の賃金については当然法律上も定めがなく、無給と定めることも差し支えありません。実務上は健康保険加入者であり、かつ、労務不能である旨の意思の証明が取得できれば傷病手当金が支給されます。支給額については給与相当額の概ね6割ですが、非課税である点は労働者としてもメリットとなります。
また、私傷病休職中については、産前産後、育児休業期間中とは異なり、社会保険料は免除されません(制度自体が存在しない)。よって、私傷病休職中は無給と定めている場合は当該期間中の社会保険料をどのように負担するかの合意を取得しておく必要があります。無論、社会保険料は労使折半であり、言葉を選ばず申し上げると私傷病期間中だからといって会社が全額負担しなければならないということはありません。実務上は会社が指定する口座へ振り込んでもらう等が想定されますが、その際の振込手数料をどちらが負担するかも決定しておくべき論点です。
最後に私傷病休職から復職にあたっての判断です。特にメンタルヘルス問題が契機となった私傷病休職の場合は外見からは判断が難しく、医学的な判断が必要不可欠です。会社が常時50人以上の労働者を雇用する企業であれば、労働安全衛生法上、産業医の選任義務があり、当該産業医と面談することが考えられます。あるいは産業医ではなく、主治医から診断書を取得し、復職にあたっての判断材料とすることも考えられます。ここでの問題として、産業医と主治医の見解が割れる場合です。産業医の場合は事業場の労働環境等を総合的に勘案しつつ医学的な判断となるのに対し、主治医の場合は休職者の事業場に籍があるわけではなく、当該労働環境まで見据えた医学的判断とはならず、むしろ見解が一致しないケースも少なくありません。会社としても安全配慮義務の観点から拙速な判断はできず、かつ、未完全な状態での労務提供を受領する義務もないことから慎重な判断とならざるを得ません。
ストレスチェック
メンタルヘルス問題が大きな問題となる前に事前に芽を摘むことができればそれに越したことはありません。常時50人以上の労働者を雇用する企業であれば、ストレスチェックが義務化されています。ただし、それ未満の企業であってもストレスチェックを活用することでメンタルヘルス問題が大きな問題となる前に事前に芽を摘むことが可能になりますが、実施が難しい場合は定期健康診断での異変の発見です。ただし、要配慮個人情報にあたり、取扱いに当たっては特定の職員に限定して取扱い可とするなどのリスク管理が重要です。
ストレスチェックに話を戻すと、「集団分析」が行われ、その結果をどのように活用して職場環境の改善に繋げるかにフォーカスをあてるべきです。また、集団分析の結果はあくまで労働者の主観的なストレスの平均値であり、これのみで事業場内の問題を把握できるとは考えるべきではありません。しかし、得られた結果からも何らかの解釈が可能であり、上長との主観と一致しているか、繁忙期はどのような変化を示すか(ストレスチェック実施時期と繁忙期が合致していないケースは要注意)は注視すべき部分です。
最後に
メンタルヘルス問題の難しさは、仮に10人の労働者がいれば10通りの性格やバックグラウンドが存在し、それぞれ感じ方も異なるとういうことです。すなわち、数学的な正解が存在しないため、画一的な判断ができないという由々しき問題があります。しかし、企業としても歩みを止めるわけにはいかず、個々の職場において、メンタルヘルス問題がどのようなことが引き金となり起きやすいのか、仮に起きてしまった場合にどのような対策が被害を最小限に留められるかに着目し、労務管理を進めていくことが重要です。

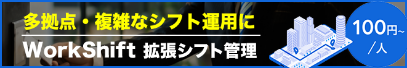


 IT企業のオフィスの特徴と労働生産性の向上について
IT企業のオフィスの特徴と労働生産性の向上について  試用期間の実態とは?有給休暇・解雇・労働基準法のポイントを徹底解説
試用期間の実態とは?有給休暇・解雇・労働基準法のポイントを徹底解説  人時生産性(にんじせいさんせい)って何?
人時生産性(にんじせいさんせい)って何?  【企業向け】経費精算の不正でよくあるケースを紹介。具体的な対策方法も紹介
【企業向け】経費精算の不正でよくあるケースを紹介。具体的な対策方法も紹介  人をサポートする仕事!労務のキホン
人をサポートする仕事!労務のキホン 